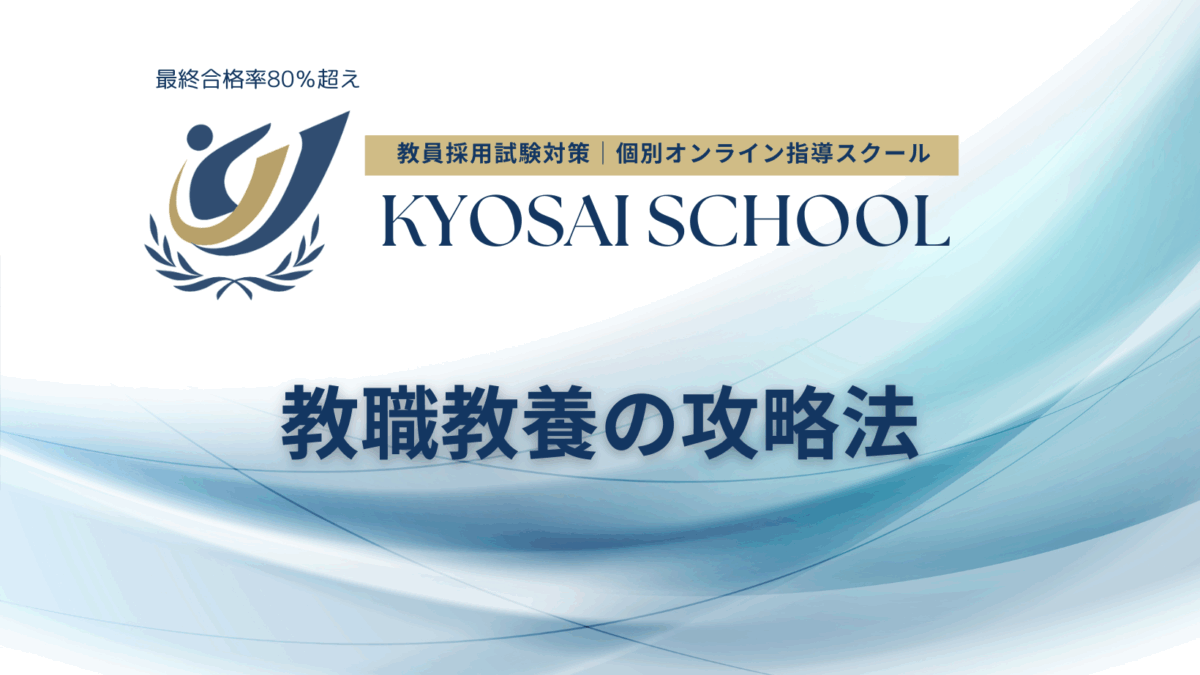教職教養は範囲が広く、暗記だけではなく理解・整理・活用力が必要な分野です。
以下の流れで学習すると、効率的に得点力を高められます。
1. 全体像をつかむ
- まず出題範囲を把握しましょう。教職教養は大きく以下に分かれます。
- 教育原理(教育の目的、制度、教育史など)
- 教育法規(教育基本法、学校教育法、学習指導要領など)
- 教育心理(発達段階、学習理論、心理学用語)
- 教育時事(新しい学習指導要領改訂ポイント、教育ニュース)
- 過去問や模試の分析で「どこが頻出か」を把握してから学習計画を立てることが重要です。
2. 頻出テーマから学ぶ
- 出題頻度の高い分野(例:教育基本法の条文番号、ピアジェ・エリクソンの発達段階、学習指導要領の総則)を先に固める。
- 苦手分野を後回しにすると全体像が曖昧になるので、まずは「基礎の土台」を作ることを優先します。
3. アウトプット中心の学習
- 教職教養は「見たことはあるけど答えられない」が起きやすい分野。
- 暗記カードや一問一答アプリを活用し、短時間で繰り返す。
- 過去問は解くだけでなく「なぜその答えなのか」を説明できる状態にする。
4. 教育法規は条文と背景をセットで覚える
- ただの丸暗記ではなく「なぜこの条文があるのか」「現場でどう使われるか」をイメージする。
- 条文番号やキーワードは 語呂合わせ や ストーリー化 で記憶を長期化。
5. 教育心理は図と比較で覚える
- 発達段階(ピアジェ、エリクソン、コールバーグ)や学習理論(スキナー、バンデューラ)は表や図にまとめると混同しにくくなります。
6. 教育時事は定期的に更新
- 文科省HPや教育新聞などで新しい情報をチェック。
- 模試や予想問題集の「最新時事分野」を必ず解いておく。
7. 学習サイクル例(1日30〜60分×3回)
- 朝:暗記カード・一問一答で復習(インプット)
- 昼:過去問を1テーマずつ解く(アウトプット)
- 夜:間違えた部分の解説読み+まとめノート整理
8. 最後の1ヶ月は模試形式で総仕上げ
- 時間を計って解き、本番の感覚をつかむ。
- 間違えた箇所は「なぜ間違えたか」を必ずメモして、同じミスを防ぐ。
📌 ポイント
- 広く浅くではなく、「出るところを深く」
- 反復回数で定着させる
- 条文や理論は意味と背景を理解して覚える