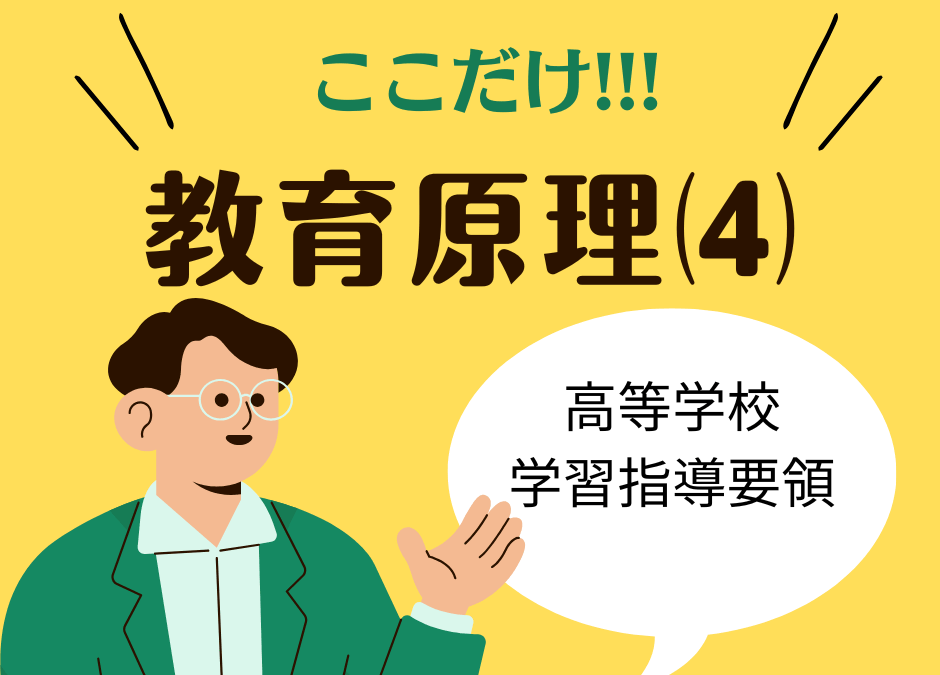―「単位制」で何が変わる?進路実現を支えるカリキュラムの仕組みをおさえよう!―
はじめに
高等学校の教育は、高等学校学習指導要領(平成30年告示)を基盤とし、義務教育段階(中学校)で培った学びを受けて、生徒一人ひとりの心身の発達および進路に応じて「高度な普通教育」と「専門教育」を施すことを目的としています。教育現場が注目する大きな特徴は「単位制」と「進路指導の充実」です。
この章では、以下の必修ポイントを整理していきます:
- 高校の目的(高度な普通教育・専門教育・進路決定)と小中学校との接続
- 卒業要件・単位の仕組み
- 必履修教科・科目の構成と学校設定教科・科目の役割
- キャリア教育および就業体験活動
- 義務教育段階の学習内容が定着していない生徒への配慮
1. 高校の目的と接続性
高校は義務教育を終えた生徒が次のステージに進む場です。義務教育で「基礎的な学び」が整えられていることを前提に、高校では次のような目的が定められています:
- 高度な普通教育:国語・数学・外国語などを深め、大学進学や社会での基盤を育てる。
- 専門教育:農業・工業・商業・看護・福祉など専門学科において、将来の職業・進路選択に備える学びを行う。
- 進路決定支援:生徒が自らの将来を見通し、進学・就職等の進路を具体的に決めていく過程を支援する。
このように、中学校までの「幅広く基礎を固める」学びから、高校では「深めて選択していく」学びへと接続していくわけです。
2. 卒業要件と単位の仕組み
高校卒業には、一定の単位数の修得が必要です。下記はその仕組みの主要ポイントです。
- 卒業までに修得すべき単位数:74単位以上。
- 単位の計算基準:1単位は「35 単位時間(1単位時間50分)を基準として算定」されます。
- 授業時数の標準(全日制):年間35週が基本。週当たり約30 単位時間が目安となる学校もあります。
- 単位制とは:学年制とは異なり、決められた単位を修得すれば卒業が認められる制度。生徒のペース、興味関心に応じた学びが可能です。
この「単位制」の導入によって、生徒自身の選択や進度に応じて教育課程を編成・履修できるようになりました。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
3. 必履修教科・科目と学校設定教科・科目
高校では、すべての生徒が履修すべき「必履修教科・科目」が定められています。さらに、生徒や地域の実態・特色を反映させるため、「学校設定教科・科目」を設けることも可能です。
- 必履修教科・科目:例えば、公共、地理歴史・地理総合・歴史総合、情報Ⅰ、英語コミュニケーションⅠなど。これらはすべての生徒に共通して履修させる必要があるものです。
- 学校設定教科・科目:設置学校の特色や地域実態に応じて独自に開設できる教科・科目です。例えば「産業社会と人間」など、必履修に代えて設定される場合もあります。
- 専門学科の場合、専門教科・科目を一定単位以上履修することで、普通教科の履修を一部代替できる制度もあります。
この構成により、生徒の進路希望・学校の特色が教育課程に反映されるようになっています。
4. キャリア教育と就業体験活動
高校では、「どこへ進むのか」「何をめざすのか」という進路決定が重要となる時期です。そのため、次のような取り組みが重視されます:
- キャリア教育の強化:将来の職業・社会参加を視野に入れ、生徒が自分の興味・関心・能力を振り返る機会を設けます。
- 就業体験・企業連携:長期間のインターンシップ・職場体験などを通じて、実際の仕事の世界を体験し、進路決定に資する実践的な学びを行うことが求められます。
- 義務教育段階の内容の指導:学習の遅れが見られる生徒について、高校入学段階で義務教育(中学校)内容の定着を図る指導を併用する配慮も明記されています。
これらにより、生徒が社会とつながりながら、進路を主体的に選び、歩んでいくための基盤づくりが進められています。
5. 学習の遅れがちな生徒への配慮
高校入学時点で義務教育段階の学習内容が十分に定着していない生徒については、以下のような配慮が求められています:
- 必履修教科・科目の履修を進める前又は並行して、義務教育期の内容の定着を図るための「学校設定教科・科目」を設けてもよい。
- 教育課程全体を通じて、生徒一人ひとりの学びの実態を把握し、必要に応じて支援を行う体制を整えることが重要です。
このような「つまずきへの配慮」が、高校段階での学びの充実・進路実現につながっていきます。
まとめ
- 高等学校では「高度な普通教育」「専門教育」「進路決定支援」が目的となっており、中学校からの接続を意識した学びが求められます。
- 卒業要件として74単位以上の修得が必要であり、単位制の仕組みによって生徒の選択・履修が柔軟に設計されています。
- 必履修教科・科目と学校設定教科・科目の違いや役割を明確に理解することが重要です。
- キャリア教育・就業体験活動が一層重視され、生徒が社会・職業に目を向けた学びをするよう制度設計されています。
- 学習の遅れがある生徒には、義務教育段階の内容の定着を図るための特別な配慮が組み込まれています。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
教採スクールからのメッセージ
「単位制」「進路指導」「キャリア教育」という言葉だけで終わらせず、「なぜこの制度が必要か」「どう生徒の学びを支えるか」という視点で捉えておくと、試験だけでなく教員としての実践力も養われます。ぜひ、自分なりに「高校でこんなカリキュラム構成をしたらどうか?」と仮設を立ててみてください。