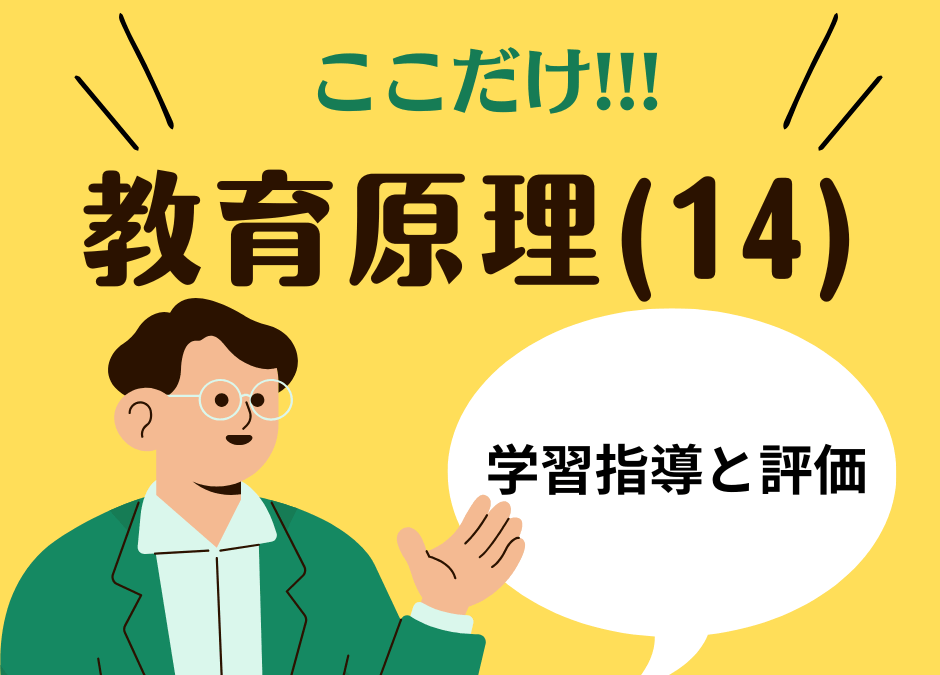学習指導と評価の原理
授業の質を高める「指導と評価の一体化」
必修ポイント
- 指導と評価の理念(指導改善と学習意欲向上)と、学習評価の3観点を理解する。
- ブルームの3つの評価(診断的・形成的・総括的)と目的の違いを区別する。
- 学習指導の形態(一斉・個別・小集団)の長所・短所と、協同学習(バズ・ジグソー)の提唱者を正確に押さえる。
- パフォーマンス評価、ポートフォリオ評価、ルーブリック評価の特質を把握する。
なぜ「指導と評価の一体化」が重要か
学習評価は成績決定だけが目的ではありません。評価で得た情報を授業改善へつなぎ、学習者の自己調整と学習意欲を高めることが現代の教育の基本原則です。単元設計の段階から「何を・どの程度できるようにするか(パフォーマンス基準)」を明確にし、指導・評価・課題設計を揃えることが要点です。
1. 学習評価の3観点(資質・能力に対応)
- 知識・技能
概念理解・語彙・手続き的技能などを測定。ペーパーテストや観察で把握。 - 思考力・判断力・表現力等
課題解決の過程、論述・レポート・発表、探究プロセスなどで評価。 - 主体的に学習に取り組む態度
目標設定・粘り強さ・ふり返り等の意思的側面を重視(挙手回数など形式的指標のみで評価しない)。
評価は「単元のまとまり」で計画し、ペーパーに偏らない多面的・多角的な方法を組み合わせます。
2. ブルームの教育評価(3類型)
| 類型 | 実施時期 | 目的 | 主な手法 |
|---|---|---|---|
| 診断的評価 | 指導前 | レディネス・つまずきの予見 | 事前テスト、面談、K-W-L 等 |
| 形成的評価 | 指導中 | 指導改善・補充と発展 | 小テスト、観察記録、ミニルーブリック、ピアレビュー |
| 総括的評価 | 指導後 | 到達度判定・成績決定 | 単元末テスト、課題成果物、最終発表 |
※特に形成的評価は「今、何をどう直せば到達できるか」を明示するフィードバックが核です。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
3. 学習指導の形態と協同学習
学習形態の比較
| 形態 | 長所 | 留意点・短所 | 代表的手法 |
|---|---|---|---|
| 一斉学習 | 系統的指導・全体最適 | 個別差への対応が難しい | 講義法、問い返し、全体討議 |
| 小集団(グループ) | 相互作用で深い理解・社会性育成 | 役割偏在・ただ乗り防止の設計が必要 | バズ学習、ジグソー学習 |
| 個別学習 | 学習者主導・到達度最適化 | 規律・自己管理の支援が必要 | プログラム学習、ドリル、ドルトン・プラン的運用 |
協同学習の代表と提唱者
- バズ学習(6・6討議)… フィリップス
- ジグソー学習 … アロンソン
いずれも「個で学び、対話で深め、再び個に戻す」設計(個別→協同→個別)が効果的です。
4. 多面的評価の道具と使い分け
| 評価法 | ねらい | 特徴 | 活用例 |
|---|---|---|---|
| パフォーマンス評価 | 実際の課題遂行能力を測る | 本物課題(話す・書く・作る・調べる)で観察 | 実験レポート、口頭試問、プレゼン |
| ポートフォリオ評価 | 学習の過程と成長を可視化 | 作品・下書き・自己評価・教師コメントを継時保存 | 単元フォルダ、リフレクションシート |
| ルーブリック評価 | 到達基準の透明化 | 観点×水準のマトリクスで明確化・自己評価可能 | 3観点×4水準の単元ルーブリック |
ポイント
- 事前に基準を共有(受審者が基準を知っていること)。
- 形成的に使い、次の行動に結びつく具体フィードバックを短周期で返す。
- 3観点と一貫する観点設計にする(知識・技能/思考・判断・表現/主体的態度)。
5. 授業デザインへの落とし込み(実装チェックリスト)
- 目標整合:単元目標を3観点で言語化し、評価課題と完全に整合させる。
- 本物課題:単元末はパフォーマンス課題(アウトプット)で「使える知」を測る。
- 形成的評価:ミニルーブリックや出口チケットで学習途中のズレを修正。
- 協同学習:役割・評価・振り返りを設計し、社会的スキルの学習目標も明示。
- 主体的態度:目標設定→自己点検→次の手立てをルーチン化(リフレクション)。
- エビデンス保管:ポートフォリオ(成果物+ふり返り+指導者コメント)で成長を可視化。
6. すぐに使えるミニテンプレート
単元ルーブリック(例:説明的文章の要約)
| 観点\水準 | 4 到達 | 3 標準 | 2 部分到達 | 1 初期 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 重要語句と構成を正確に抽出 | ほぼ正確に抽出 | 抜け・誤りがある | 抽出が不十分 |
| 思考・判断・表現 | 要旨と根拠を論理的に再構成 | 概ね論理的 | 論理の飛躍あり | 列挙のみ |
| 主体的態度 | ふり返りで改善点を次回に反映 | ふり返りを記述 | 表面的な記述 | 記述なし |
形成的評価の小道具
- 入口テスト(診断的)→ グルーピングと補充設計
- 出口チケット(形成的):「今日できたこと/次回の課題」
- 3分プレゼン+ピア・ルーブリック(形成的)
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
まとめ
- 学習評価は「測って終わり」ではなく、学習者の成長と授業改善のエンジン。
- 3観点に揃えた目標・課題・評価基準を設計し、形成的評価で学びを動かす。
- 指導形態は目的に応じて使い分け、協同学習は役割と評価を明確に。
- パフォーマンス・ポートフォリオ・ルーブリックを組み合わせ、学習の過程と成果を可視化する。
授業の「効果最大化」は、明確な到達基準の共有と、短周期・具体的なフィードバックから始まります。
教員採用試験「一発合格」に自信あり!
◇教員採用試験最終合格率82%以上!
◇倍率30倍以上の校種合格実績多数!
◆最新情報はコチラへ
****************
「教採スクール」の合格メソッド
****************
「教採スクール」では 受講生の学習歴や特長などパーソナルまで理解して『学習管理型個別指導』の形態を取っており、元校長先生を受講生担当の学習コーチとして個々に配置しています。
また日々学習をサポートする学習コンサルタントが別で配置され受講生の【教員採用試験】学習進捗管理とWEBコンテンツの視聴や利用管理を行なっております。この受講生支援の手厚さが合格に導くメソッドです。
◆最新情報はコチラへ
【教員採用試験90日間合格メソッド】
【画像をクリックして下さい❗️】
📩 LINE公式「教採スクール」でも教員採用試験情報や教育コラム配信中!
”STAY LEARNING, STAY GROWING.” —— 学び続け、成長し続ける。
須合 啓(教採スクール 代表)
<経歴> 埼玉県公立高校教諭 12年 教採スクール運営 13年
<合格実績> 教員採用試験「65受験地」全員合格実績あり
<書籍>
「自分で考えて動ける子の育て方」(2022年10月/明日香出版)
「自分から進んで学ぶ賢い子の育て方」(2024年8月/明日香出版)