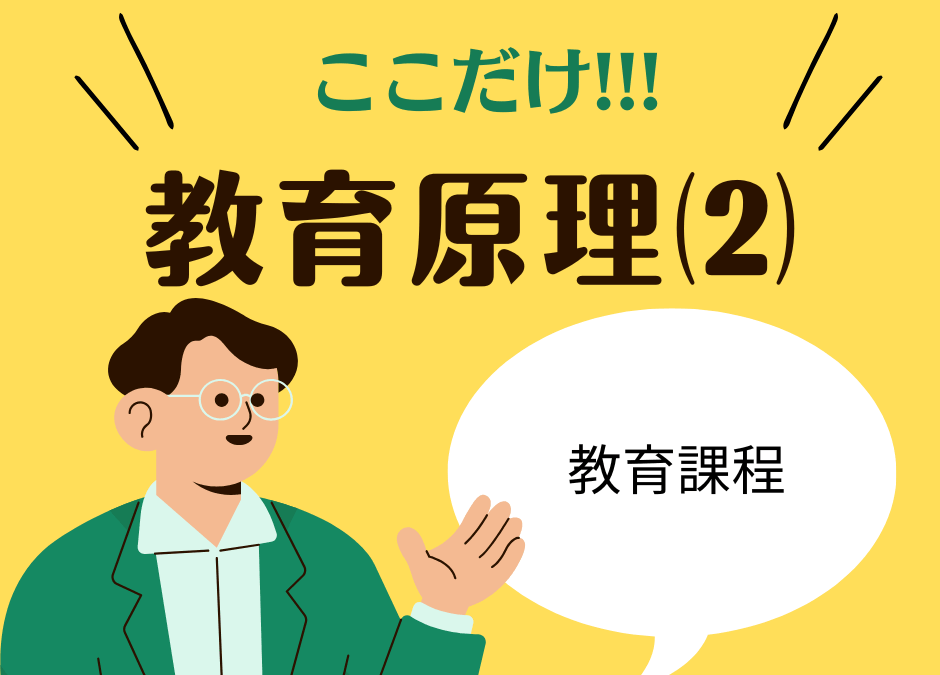―「カリキュラム」とは何の計画?5つの類型と編成の原則をおさえよう!―
はじめに
学校教育の目的を実現するためには、児童・生徒の心身の発達に応じて、授業時数や学習内容を含む教育内容を総合的に組織する必要があります。これが「教育課程(カリキュラム)」です。ラテン語で「競走の走路(curriculum)」に由来し、教育目標というゴールに向けて“学びの道筋”を示す設計図とも言えます。
この章では、教員採用試験でも頻出の「教育課程の定義」「カリキュラムの類型」「編成の基本要素」「教科主義と経験主義」という観点を整理し、実践に活かせる見方を身につけましょう。
1. 教育課程の定義と国家基準としての学習指導要領
定義: 学校教育法を背景に、各学校の校長の責任のもと、全教職員が協働して編成する教育計画を指します。
国家基準としての役割: 学習指導要領は、教育課程の国家基準であり、文部科学大臣が公示し、すべての学校が遵守すべき法的拘束力を持つものです。これにより、全国の学校で教育水準が一定に保たれています。
編成の基本要素: 教育課程をつくる際には、次の3つの要素を統合的に検討することが重要です。
- 目標(教育で何を目指すか)
- 内容(何を学ばせるか)
- 方法(どのように教え、学ばせるか)
この三位一体の観点から教育を設計し、さらに「計画 → 実行 → 評価 →改善(PDCAサイクル)」を回す仕組みが求められます。
顕在的・潜在的カリキュラム: 明文化された時間割やシラバスなどが「顕在的カリキュラム」です。一方で、学校の雰囲気、教師の態度、生徒同士の人間関係など、意図して計画されていない学びや価値形成が「潜在的カリキュラム」です。こちらも児童・生徒の成長には大きな影響を持つため、見逃せません。
2. カリキュラムの主要な類型(5つ+α)
カリキュラムは、「何を“核(中心)”として教育内容を構成するか」によってさまざまな類型に分類できます。これらを理解しておくと、出題側の意図や授業設計の観点が明確になります。
以下に主要な類型を整理します。
| 類型 | 核となるもの | 特徴・応用例 |
|---|---|---|
| 教科カリキュラム | 知識の系統性・論理性 | 国語・数学など、伝統的な教科を体系的に構成。教科主義の典型。 |
| 経験カリキュラム | 児童・生徒の興味・生活経験 | 生徒の関心・生活を起点に教材を構成。経験主義的発想。 |
| 相関カリキュラム | 関連性の高い複数の教科 | 教科の枠を維持しつつ、内容のつながりで学習効果を高める(例:低学年で社会・理科を生活科に統合)。 |
| 融合カリキュラム | 教科の境界を解体・再構成 | 地理・歴史・公民を「社会科」に統合、など。教科間の壁を低くする。 |
| 広領域カリキュラム | 大きな学習領域 | 「人文科学」「自然科学」など大きな枠組みで再編成する。 |
| コア・カリキュラム | 現代社会の共通課題(核) | すべての生徒が共通に学ぶべき“核”を置き、その周辺に基礎教科を配する構成(たとえば、アメリカでの「コア・カリキュラム」構想)。 |
覚え方のポイント:
“知識系”なら教科カリキュラム、“経験系”なら経験カリキュラムというように、「核」がどこにあるかという視点で整理すると理解しやすくなります。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
3. 教育課程編成の3つの基本的要素
教育課程を編成する際には、次の3要素を明確にしておくことが鍵です。
- 目標 – 学校教育で何を育てたいか、どんな知識・能力・態度を身につけさせたいか。
- 内容 – その目標を実現するために、どのような学習内容を扱うか。教科内容・領域・活動などを設計します。
- 方法(指導) – 生徒がその内容を学び、目標に近づくためにどのように教えるか。授業形態・活動形式・評価方法なども含みます。
この3つを“並列”ではなく“統合的”に見直しながら、授業設計・学年計画・学校全体の教育課程を考えることが重要です。
4. 教科主義 vs. 経験主義
教育課程をめぐる大きな対立軸として、「教科主義」と「経験主義」があります。
- 教科主義:知識・技能を体系的・論理的に構成することを重視します。教科を中心に据え、学問的な構成を優先する立場です。
- 経験主義:児童・生徒の興味・経験・活動を起点に構成することを重視します。学びを生活経験から出発させ、子ども中心の教育を志向します。
現代の学習指導要領では、これら二つの視点を融合し、基礎的な知識・技能の習得を前提に置きながらも、「総合的な学習の時間」などで探究的・経験的な学びを導入しています。
まとめ
本章を通して整理したポイントは以下の通りです。
- 教育課程(カリキュラム)は、学校教育の目的を実現するために、「目標・内容・方法」を組織的に設計した学びの道筋である。
- 学習指導要領は、教育課程の国家基準として、すべての学校が守るべき枠組みである。
- カリキュラムは「何を核とするか」によって、教科・経験・相関・融合・広領域・コアなどの類型に分類できる。
- 編成にあたっては、目標・内容・方法という3つの基本的要素を統合的に検討する必要がある。
- 教科主義と経験主義という対立軸を理解することで、教育設計の背景や授業の方向性が見えてくる。
これらをしっかり押さえておくことで、教員採用試験で出題される「教育課程・カリキュラム」に関する設問に強くなります。次回は、この理論を踏まえて「典型的なカリキュラム編成手続きと事例分析」に進みます。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
教採スクールからのメッセージ
教育課程やカリキュラムの話は、一見難しく感じるかもしれませんが、「何を」「どう」「なぜ」学ばせるかを設計するという視点から見るととても実践的です。今日学んだ概念を、自分が授業を作るときに「こんな核を据えてこう編成する」という仮想で考えてみると、理解が深まります。ぜひ自分なりの設計イメージを頭に描いて、次につなげましょう。