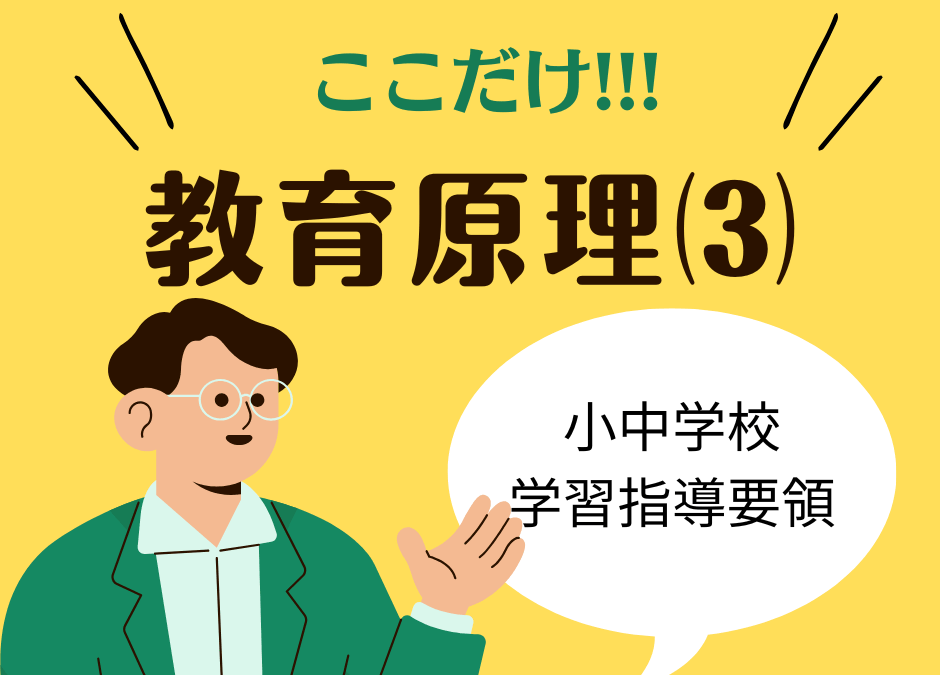― なぜ指導要領は変わった?3つのキーワードと「資質・能力」の構造をおさえよう! ―
はじめに
現行の学習指導要領(小・中学校:平成29年告示)は、変化の激しい社会を子どもたちが自立的に生き抜く力を育むために改訂されたものです。
学校教育の基本となる「教育課程の基準」として、すべての学校がこれに基づいて授業を設計・実施しなければなりません。教員採用試験でも、学習指導要領の構造と改訂の意図は頻出テーマです。
ここでは、その3つの改訂の柱と資質・能力の3要素を中心に整理していきましょう。
1. 学習指導要領の法的役割
学習指導要領は、文部科学大臣が公示する「教育課程の基準」であり、全国すべての学校に法的拘束力を持つ国家基準です。
この基準があることで、全国どこでも一定の教育水準が保たれ、教育の機会均等が実現されています。
学校現場では、この要領をもとに各教科や領域の学習内容・方法を組み合わせ、教育課程(カリキュラム)を編成していきます。
2. 改訂の3つの柱(キーワード)
今回の改訂は、次の3つの基本理念に基づいています。これらは教員採用試験の定番出題ポイントです。
(1)社会に開かれた教育課程
学校と社会が目標を共有し、互いに連携しながら教育活動を行うという考え方です。
地域や企業、家庭などと協働して教育を進め、子どもたちが「社会の一員として生きる力」を育むことを目指します。
→ キーワード:開かれた学校・地域連携・学びの社会化
(2)カリキュラム・マネジメント
各学校が自校の教育目標を踏まえて教育課程を編成→実施→評価→改善する仕組みのことです。
学校全体でPDCAサイクルを回しながら教育の質を高める「組織的な教育課程管理」とも言えます。
特に校長がその責任者となり、学校運営と一体化して行う点が特徴です。
→ キーワード:PDCA・学校経営・校長のリーダーシップ
(3)主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)
単なるグループ活動ではなく、「学び方の質」を高めるための授業改善の視点です。
- 主体的な学び: 自ら課題を見いだし、見通しを持って学ぶ態度
- 対話的な学び: 友達や教師との対話・協働を通して学びを広げる態度
- 深い学び: 習得した知識を活用し、課題を多面的・多角的に考える力
この3つの観点を授業に取り入れることで、思考力・判断力・表現力を育て、学びが子どもの中で“つながる”ようにします。
→ キーワード:学習過程の質・授業改善・学びの主体化
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
3. 育成をめざす「資質・能力」の3つの柱
学習指導要領は「何を教えるか」ではなく、**「何ができるようになるか」**という成果の観点で整理されました。
育成を目指す資質・能力は、次の3つの柱で構成されています。
| 柱 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 知識・技能 | 生きて働く知識や技能を確実に習得する。 | 「覚える」だけでなく「使える」知識へ。 |
| 思考力・判断力・表現力等 | 習得した知識・技能を活用して課題を解決する力。 | 「考える力」「自分の言葉で表す力」。 |
| 学びに向かう力・人間性等 | 学びを社会に生かそうとする態度、自己肯定感、他者との協働の姿勢。 | 「意欲」「関係性」「人間としての成長」。 |
この3つは、単独ではなく互いに関連し合い、“知識→活用→人間性”という学びの循環を生み出します。
試験では、「どの柱に該当するか」を区別できるようにしておきましょう。
4. 教育課程編成の原則と時間規定
(1)教科等横断的な視点
「言語能力」「情報活用能力(プログラミング的思考を含む)」「問題発見・解決能力」などの学習の基盤となる資質・能力は、特定の教科だけでなく、すべての教科・領域を通して育成します。
これは、教科横断的な指導(カリキュラム・クロス)とも呼ばれ、実践的な学力を育てる重要な考え方です。
(2)授業時数の標準
- 年間 35週以上(小学校第1学年のみ34週以上)を標準とする。
- 1単位時間は、小学校45分/中学校50分が基準。
(3)教育課程の領域
小・中学校の教育課程は、次の5つの領域で構成されます。
- 各教科
- 特別の教科 道徳
- 外国語活動(小学校)
- 総合的な学習の時間(中学校では「探究の時間」)
- 特別活動
これらを総合的に計画し、学校全体で子どもの成長を支える仕組みをつくることが、現行指導要領の大きな特徴です。
まとめ
- 学習指導要領は、教育課程の国家基準として、全国の学校で統一的な学びを保障する役割を持つ。
- 改訂の3つの柱は、社会に開かれた教育課程・カリキュラム・マネジメント・主体的・対話的で深い学び。
- 育成をめざす資質・能力は、知識・技能/思考力・判断力・表現力等/学びに向かう力・人間性等の3つの柱で整理。
- 教科横断的な資質・能力の育成、授業時数・単位時間の規定、教育課程の5領域など、基本構造も押さえる。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
教採スクールからのメッセージ
学習指導要領は、単なる「法律」や「文書」ではなく、子どもたちの未来を設計する教育の地図です。
どんな力を育てたいのか、どんな授業をつくりたいのかを考えるとき、指導要領の理念を自分の言葉で語れることが“プロの教員”への第一歩です。