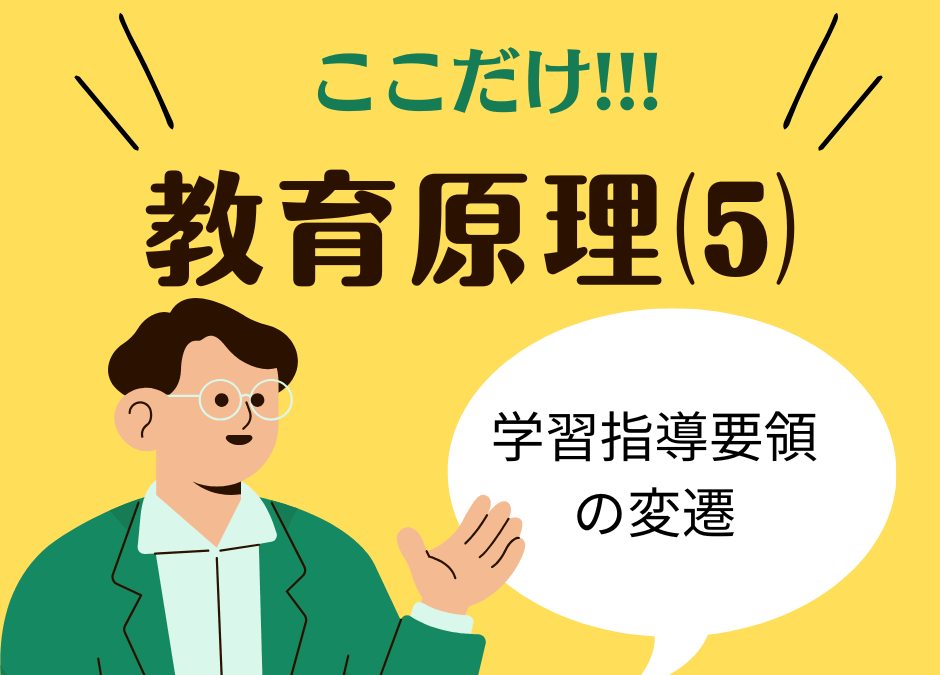― なぜ10年ごとに変わる?改訂の歴史とキーワードをおさえよう! ―
はじめに
学習指導要領は、戦後日本の教育の出発点である「民主教育」の理念をもとに、社会の変化に対応しながらおよそ10年ごとに改訂されてきました。
教員採用試験では、「年代と改訂のキーワードを正確に結びつける」ことが問われます。
この章では、学習指導要領の法的性格の確立から現行指導要領(平成29年告示)までの流れを、時代の背景とともに整理していきましょう。
1. 法的性格の確立と「教育内容の現代化」
■ 試案から告示へ
最初の学習指導要領(1947年)は、「試案」として発行され、法的拘束力を持たない“参考資料”の扱いでした。
しかし、1958年(昭和33年)改訂で「告示」形式となり、教育課程の国家基準としての法的性格が確立されました。
この改訂では、「道徳の時間」が新設され、「心の教育」が正式に教育課程に位置づけられました。
■ 教育内容の現代化(1968年改訂)
戦後復興を経て、1960年代は科学技術の発展と国際競争が激化した時代です。
特にスプートニク・ショック(1957年)を契機に、教育の高度化が急務となりました。
1968年(昭和43年)改訂では「教育内容の現代化」が打ち出され、理数教育を中心に学習内容を拡充。
例として、算数・数学に「集合」や「関数」の概念が導入され、知識量の増大と学問的体系化が進められました。
2. 「ゆとり」路線の導入と転換
■ ゆとりと精選(1977年改訂)
過密カリキュラムへの反省から、1977年(昭和52年)改訂では「ゆとりと精選」が掲げられ、授業時数が削減されました。
この方針は、詰め込み教育から脱却し、「子どもの生活体験を重視した教育」への転換を目指したものでした。
■ 「生活科」の新設(1989年改訂)
1989年(平成元年)改訂では、「ゆとり」路線を具体化する形で小学校に「生活科」が新設されました。
この科目は、低学年の子どもが生活体験や自然との関わりを通して学ぶことを目的としており、「知識偏重」から「体験的学び」へのシフトを象徴しています。
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
3. 「総合的な学習の時間」と「ゆとり教育」
■ 1998年改訂:「生きる力」の育成
1998年(平成10年)改訂では、「生きる力」の育成を理念とし、「総合的な学習の時間」が新設されました。
この改訂では、完全学校週5日制が導入され、授業時数を削減。体験活動・探究活動を重視する「ゆとり教育」が本格化しました。
しかし、その後、基礎学力の低下が問題視され、「ゆとり教育」への見直しが進みます。
4. 「脱ゆとり」と現行指導要領への流れ
■ 「確かな学力」の重視(2008年改訂)
2008年(平成20年)改訂では、「脱ゆとり」が明確に打ち出されました。
授業時数を増加させ、「基礎的・基本的な知識・技能の習得」と「思考力・判断力・表現力等の育成」の両立を重視。
また、小学校高学年に「外国語活動」が導入され、グローバル化への対応が進みました。
■ 「特別の教科 道徳」(2015年一部改正)
2015年(平成27年)には、道徳が「特別の教科 道徳」として正式に教科化。
数値評価ではなく、記述評価によって児童生徒の内面を丁寧に評価する方針が示されました。
5. 現行指導要領(2017年改訂)と新しい学び
2017年(平成29年)改訂では、急速に変化する社会(AI・ICT・グローバル化・多様性など)に対応するため、教育の方向性が大きく転換しました。
その根幹にあるのが次の2つのキーワードです。
■ 社会に開かれた教育課程
学校の学びを社会とつなぎ、地域や保護者・企業・行政と協働しながら教育を行うという理念です。
「社会の中で生きる力を育む」ことを目的に、教育課程の柔軟な編成が求められるようになりました。
■ 主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)
学びの質を高めるために、「自ら考え(主体的)」「他者と意見を交わし(対話的)」「理解を深める(深い学び)」というプロセスを重視。
さらに、育成をめざす資質・能力の3つの柱(①知識・技能、②思考力・判断力・表現力等、③学びに向かう力・人間性等)を明確にしました。
この改訂では、小学校中学年に外国語活動、高学年に外国語科が移行・新設されています。
6. 教授法の変遷と理論的背景
学習指導要領の改訂は、教育内容だけでなく、「教え方(教授法)」の進化とも深く関係しています。
古典的な「系統学習」(知識の体系化)と、デューイに代表される「経験学習」(生活経験に根ざした学び)の対立が続きながらも、現代では**両者を統合する学び(探究・協働・実践)**へと発展しています。
つまり、現行指導要領は「過去の理論の統合的発展形」として位置づけられるのです。
まとめ
| 改訂年 | キーワード | 主な内容・新設事項 |
|---|---|---|
| 1947 | 試案 | 法的拘束力なし(民主教育の出発点) |
| 1958 | 告示・国家基準化 | 道徳の時間新設、法的拘束力確立 |
| 1968 | 教育内容の現代化 | 理数教育充実、学習内容拡大 |
| 1977 | ゆとりと精選 | 授業時数削減、生活体験重視 |
| 1989 | 生活科新設 | ゆとり路線具体化、体験学習重視 |
| 1998 | 総合的な学習の時間 | 生きる力・ゆとり教育、週5日制 |
| 2008 | 脱ゆとり・確かな学力 | 外国語活動導入、授業時数増 |
| 2015 | 特別の教科 道徳 | 道徳の教科化(記述評価) |
| 2017 | 社会に開かれた教育課程 | 主体的・対話的で深い学び、外国語科新設 |
登録後メッセージに「無料相談」とお送りください。
教採スクールからのメッセージ
学習指導要領の改訂は、「社会がどのような力を次世代に求めてきたか」の反映です。
単なる年号暗記ではなく、時代背景とキーワードの意味を理解することで、教育観の変遷を立体的に把握できます。
試験では、「〇年改訂=何を目的としたか」「何が新設されたか」を正確に答えられるように整理しておきましょう。